オーストラリアで就学前のお子さんがいる方や、これからオーストラリアに引っ越す方はこちらの学校制度が気になるところだと思います。
日本と制度やしくみが似ているようで、知らないと後で後悔するような違いもあるので、学校の事は前もって調べておくことをお勧めします。
今回はオーストラリアの公立学校のしくみや、オーストラリアの小中高生が全員受ける学力テストについて解説したいと思います。
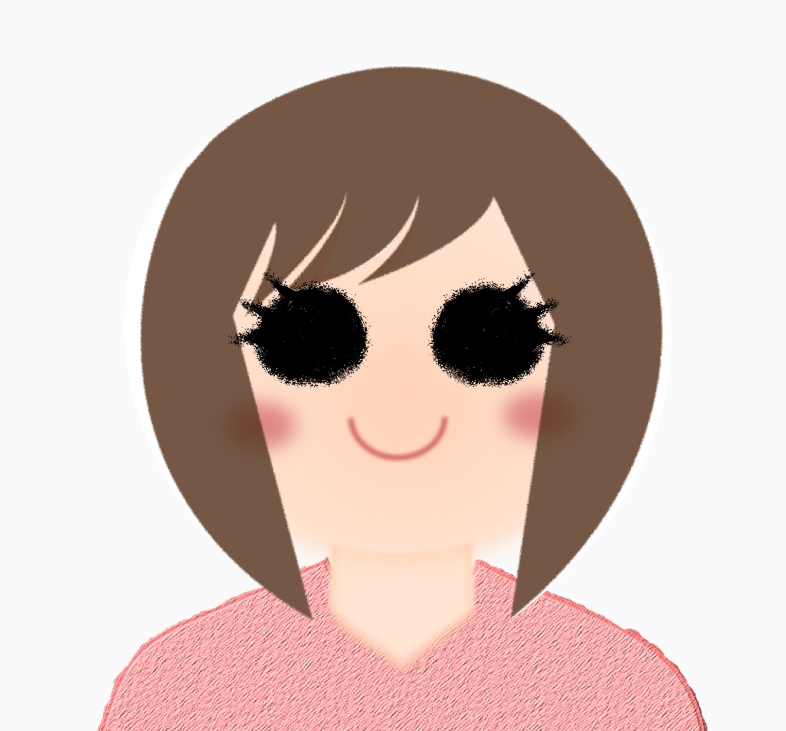
私立学校の解説は別記事でまとめているので、そちらもあわせて読んでみて下さいネ。
オーストラリアの公立学校のしくみ
オーストラリアでは公立学校が小中高と無償です。
そして日本と同じく、住んでいる場所の School Catchment 内の学校に通うのが一応のルール*です。
※学校によっては学区外の生徒でも入学申込できるところもあります。でもあくまでもキャッチメント内の生徒が優先で、定員割れした場合のみ入学が許可されます。
日本の公立学校との主な違い
日本の公立学校と似た点が多いですが、もちろん違う国なので異なる点も多々あります。
思いつく限りこんなところでしょうか。
- 小学校にも制服がある
- 中学と高校は一貫
- 義務教育は高1まで
- 公立でも男子校・女子高がある
- 公立でも学校によって学力面でかなりの差がある
小学校にも制服がある
日本では公立の小学校では制服がないのが一般的ですが、オーストラリアではハイスクールだけでなく小学校でも制服の着用が義務付けられています。
制服によってその学校の一員であることの自覚、きちんとした服の着こなしを学ぶこと、子供間の洋服格差の解消などがねらいです。
指定の制服は日本の学校と比較して大変お求めやすいお値段なので、各家庭への経済的負担も少なくて済みます。
小学校の場合は学校の指定カラーを守っていれば市販品でもOKというところもあります。(学校による)
装飾は日本ほどうるさくなく、多少のメイクやヘアカラー、ピアス、ネイルなどはOKな場合がほとんどです。
中学と高校は一貫している
オーストラリアでは
- primary school = 小学校
- secondary school (high school) = 中学・高校
と呼び、中学と高校が一貫になっています。
そもそも日本では小学1~6年生、中学1~3年生、高校1~3年生と分けるところを、オーストラリアでは小1から高3までを Year 1~12という風に一貫して数えます。
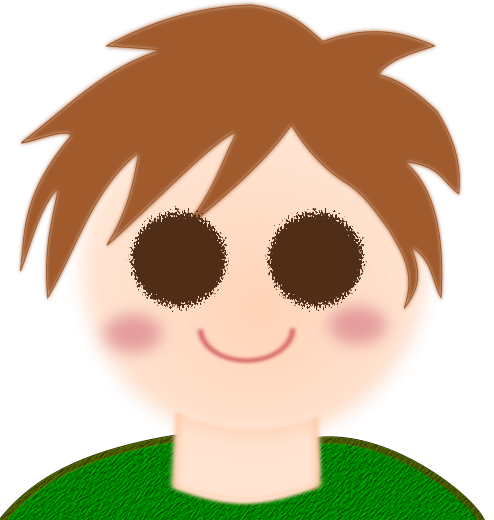
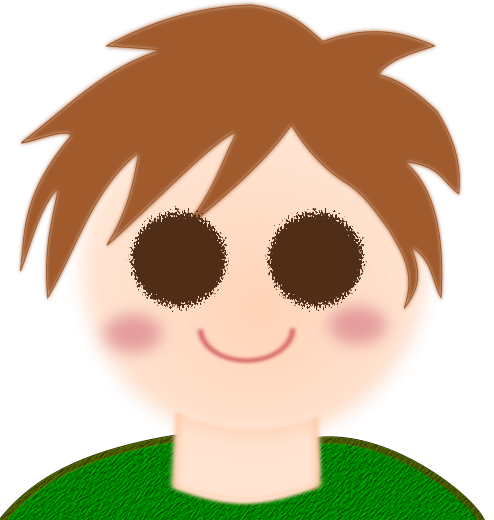
例えば中1だったらY7、高2だったらY11です。
ちなみに幼稚園は Kindy( kindergarten のこと)の頭文字をとってKと表記されます。
kindy は Year 0 とも表され、州によって呼び方が変わります。
義務教育は高1まで
オーストラリアでは義務教育は日本より一年多く、Y10までです。
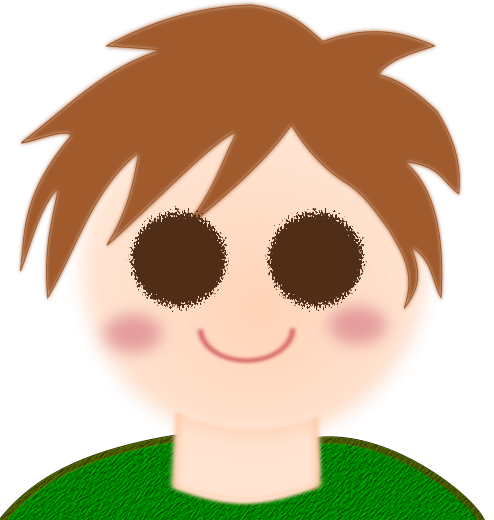
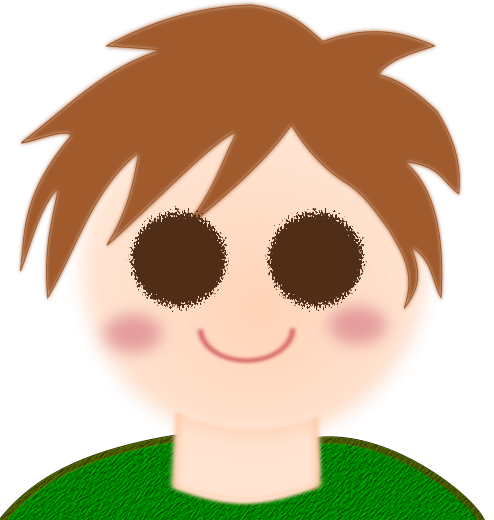
つまり高1までってこと!
Y11とY12では自分の選択科目を決めたり大学やTAFEで専門的に学ぶ前の一般教養的な事を学ぶなど、進学に向けた準備をします。
公立でも学校によって学力面でかなりの差がある
オーストラリアでは同じ公立でも地区によって学力面にかなり差があります。
その地区に多い民族の学業に対する熱の入れ方の差だったり(例えば中国系、韓国系、日系など教育に熱心な民族が多いエリアでは学校のレベルも高くなる等)、お金持ちばかりのエリアだったりと理由は様々です。
なので必然的に良い学校があるエリアは家賃相場や住宅価格が高い傾向にあります。
親なら子供を良い学校に入れたいと思うのは当然なので、生徒の学力レベルの高い学校があるエリアに人気が集中し、ますますエリア格差が広がります。
道路一本隔てただけなのに家賃相場がガクンと下がる、みたいな場合は school catchment のエリアが異なる場合があります。
安いエリアだからと思って引っ越したら学校が底辺校。。。みたいなことにもなりかねないので気を付けましょう。
小学校だったらまだ学力格差も気にならないかもしれませんが、そもそもオーストラリアは日本と比べてあまり勉強しないイメージがあるので、やはり小学校からある一定以上のレベルの学校に行かせた方が良い気がします。。。


うちのパパなんて小学校から私立で大学院まで出たのに九九も分数の掛け算もできないからね!
学校のレベルはこちらのサイトでチェックすることができますよ。
子供を通わせたい学校がギリギリ school catchment 外だとしても、裏技として入学の半年くらい前に学区内で賃貸契約をし、公共料金の書類や免許証をそこの住所にしてcatchment 内に住んでいるフリをする人もいるそうです。
噂によると学校側は一度入学を許可したらそれ以上追求しないそうですが、うまくいくかは自己責任です。
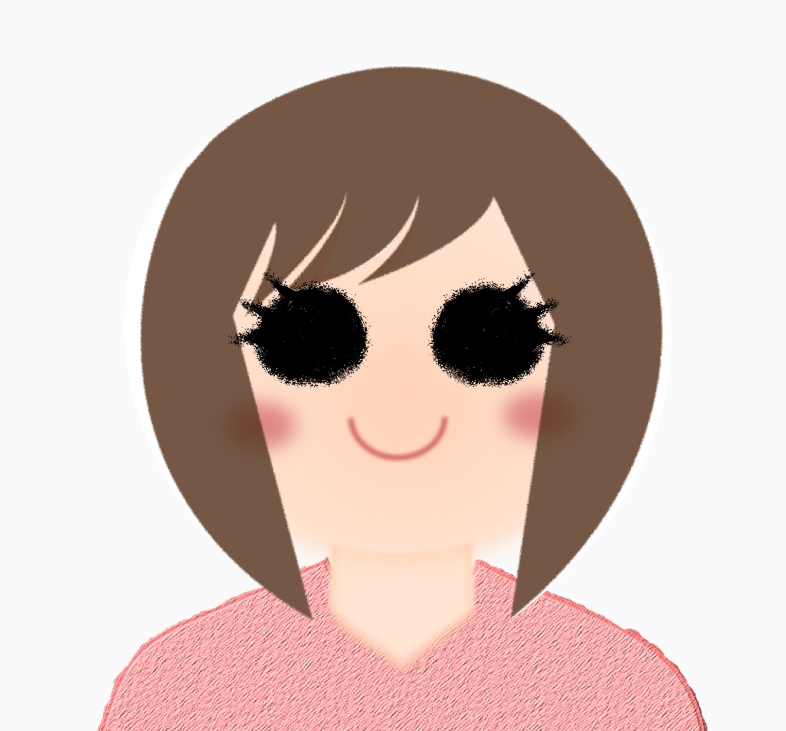
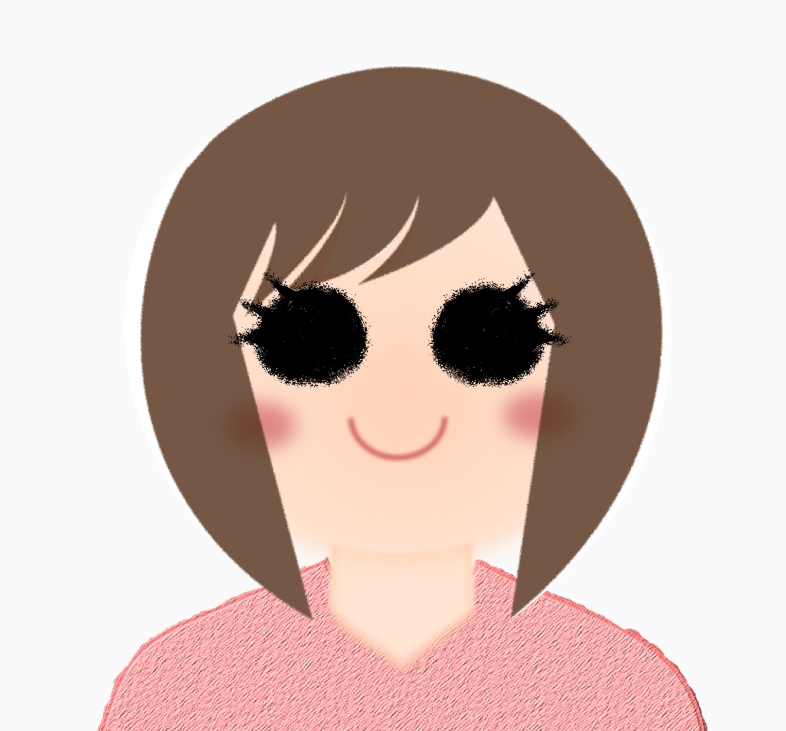
私も人づてに聞いただけなので!
オーストラリアの学生が受ける全国学力テストの種類
オーストラリアの学生が受ける全国学力テストには NAPLANと HSCがあります。
NAPLAN
NAPLAN とは the National Assessment Program – Literacy and Numeracy の頭文字をとった略で、Year 3、5、7、9 の子供たちが受ける全国テストです。
その名の通り言語能力 (Literacy)と計算能力(Numeracy)を評価するテストで、言語能力では具体的にリーディング、ライティング、文法、スペルや句読点の使い方などをみます。
評価はバンドスコアで表され、自分のスコアと全国平均を比較して得意分野や不得意分野が分かるようになっています。
NAPLAN の結果で学校全体のレベルも評価できますし、私立の学校に入学する際に NAPLAN の結果の提出が求められることがあります(学校による)。
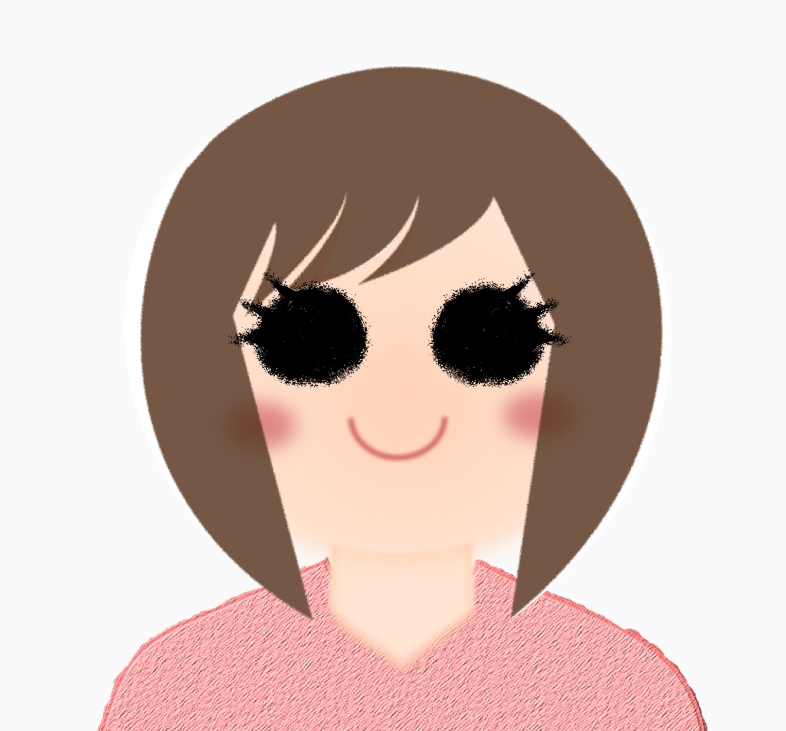
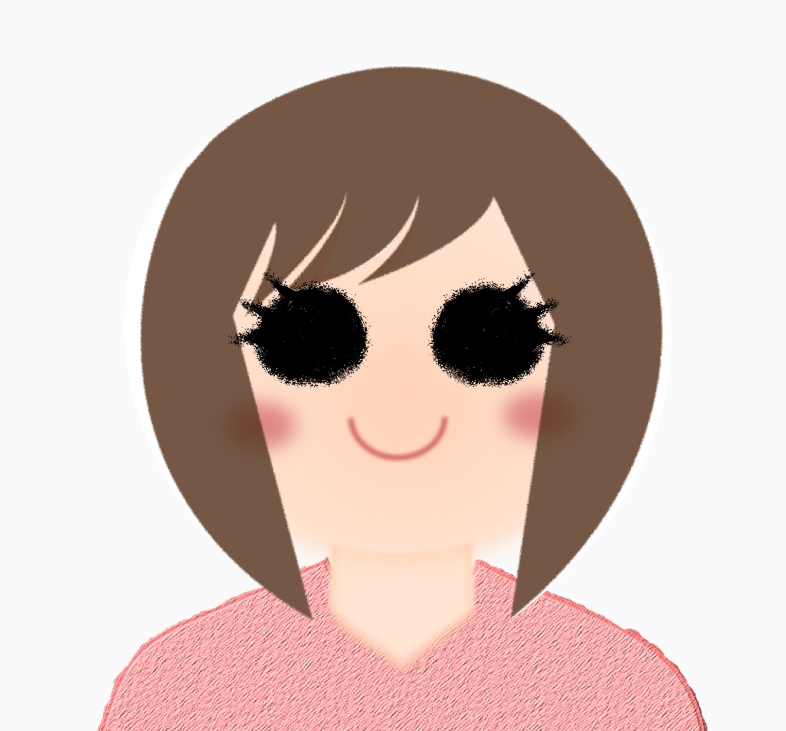
2010年の記事ですが NICHIGO PRESS にも詳しい説明が載っています。
HSC
日本で言うところのセンター試験みたいなもので、高校卒業後に受験します。
この HSC の結果が希望の大学に進学できるかに大きくかかわってきます。
HSCの結果をもとに ATAR というスコアが一人ひとりに与えられ、大学側は ATAR の数値が高い人から入学のオファーを出します。
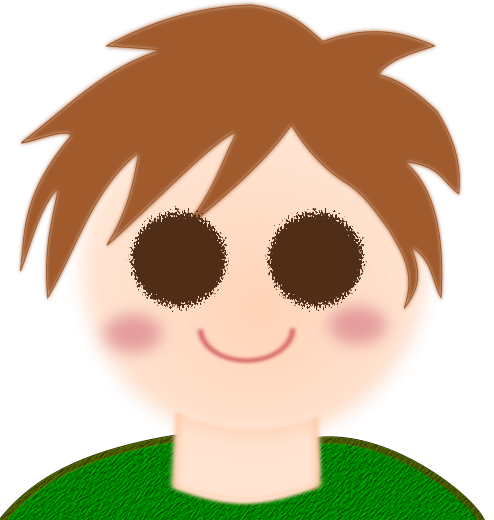
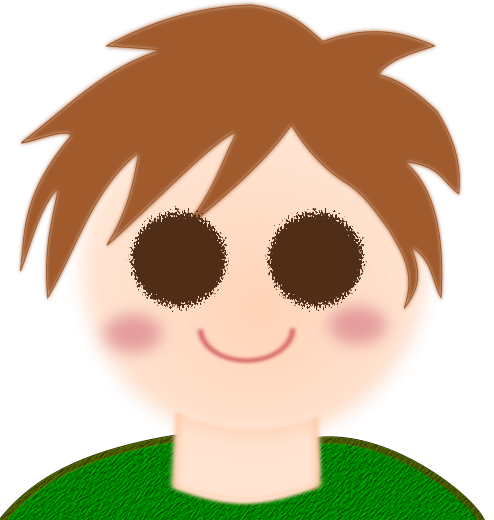
大学やコースによって ATAR の数値関係なく入学できたり、ATAR 以外の要素も加味されたりします。
マラソンで例えると HSCはタイム、ATARは順位みたいなものと考えると分かりやすいです。
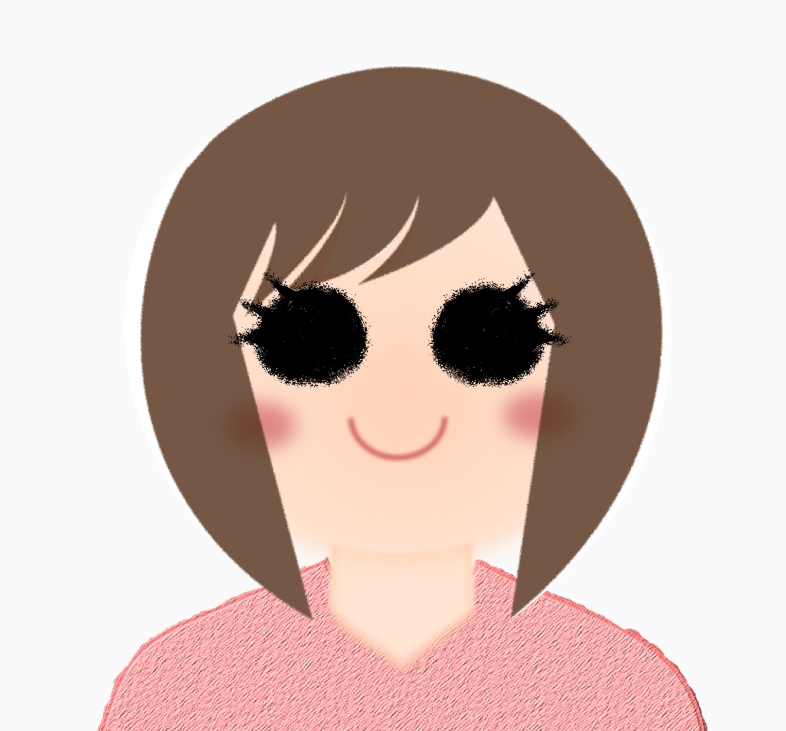
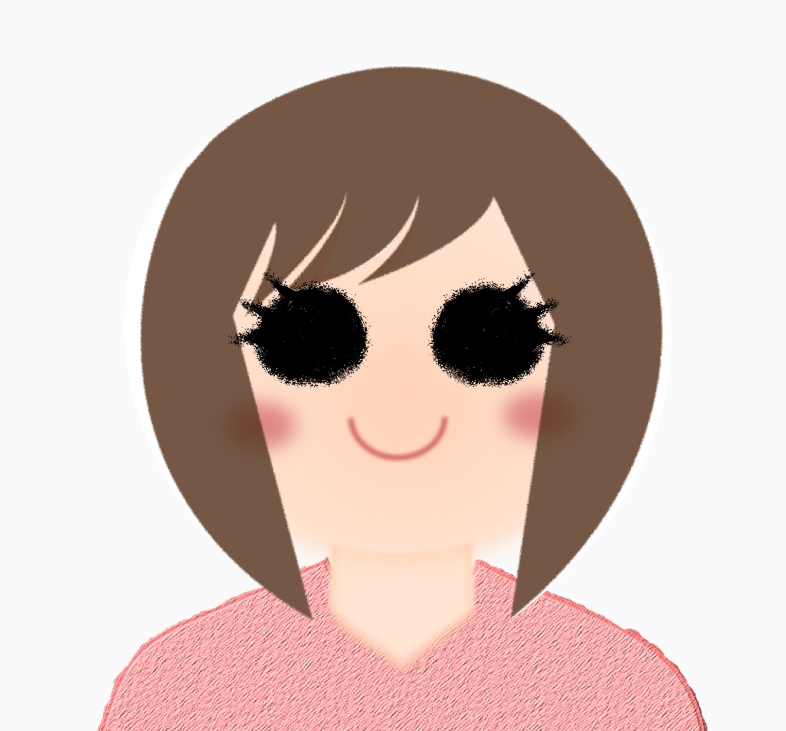
大学進学の話はまた長くなるので、また別記事にまとめようと思います。
大学進学するなら高校ではHSCを意識して勉強しましょう。
まとめ
オーストラリアの学校教育制度は日本と異なる点も多く(違う国なので当たり前ですが)、同じ公立でも頭の良い学校だったり単一民族がやたら集中している様な学校だったり、全国テストの点数がとても低かったりと様々です。
ちなみに学校をリサーチする時は学力面だけではなく民族の偏りみたいなのもチェックした方がよいです。
子供がアジア人なのでクラスメートにいじめられ転校したという話も残念ながら聞いたことがあります。
また、「学校の良し悪しは校長先生がどんな人かで決まる!」と断言していた日本人ママにも会ったことがあります。
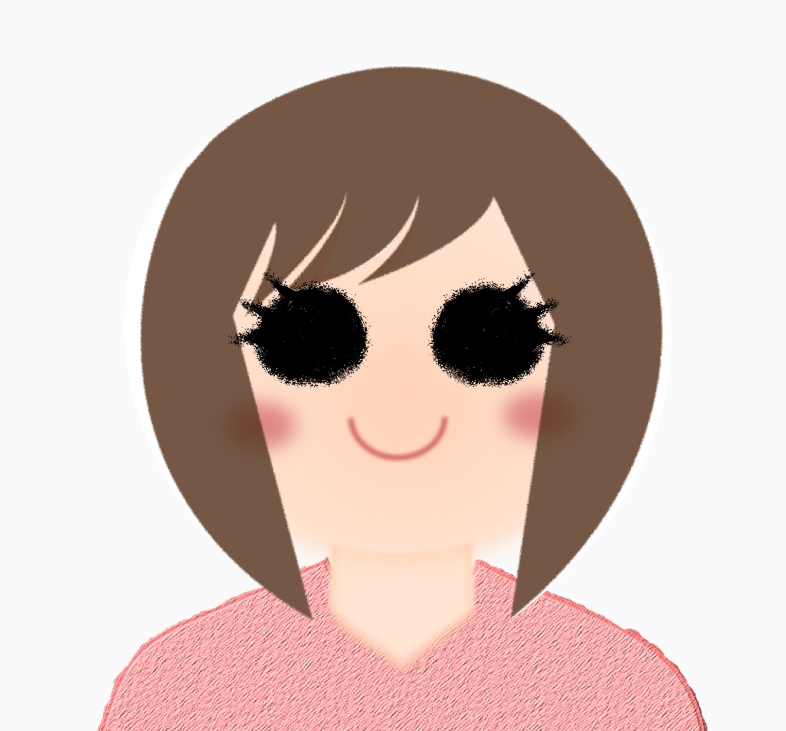
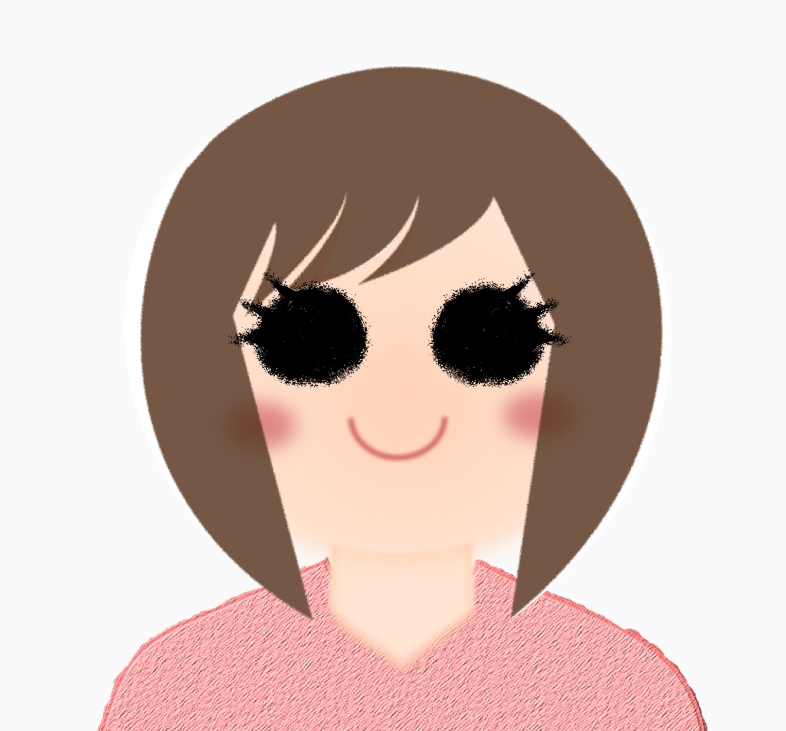
就学前のお子さんがいるなら、住む場所を選ぶときは絶対に学区内の学校をリサーチした方がよいでしょう!


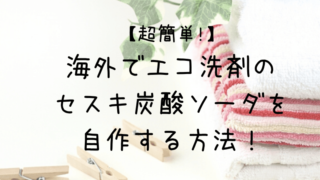


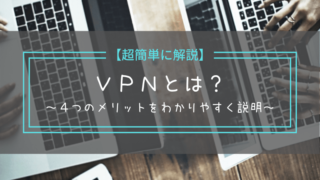

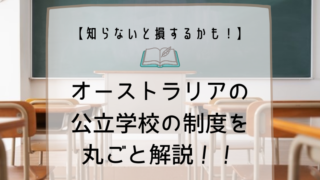

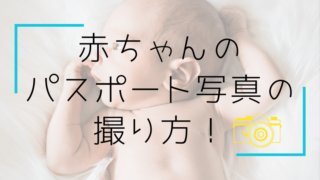



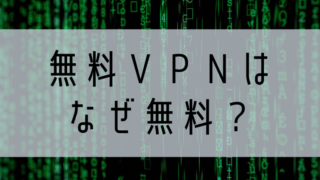

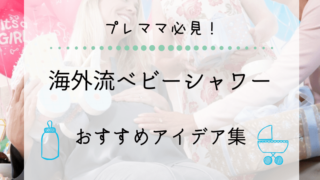

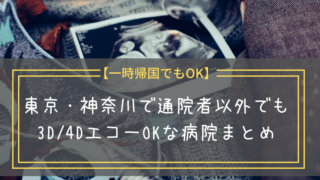


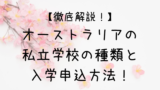



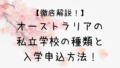
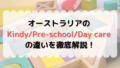
コメント