うちの一人息子は1歳9か月で「あいうえお」を覚え始めました。
2歳の誕生日を迎えた時点では「あいうえお」「かきくけこ」が、そして2か月後の現時点で「さしすせそ」「たちつてと」「なにぬねの」が(発音はともかく)言えて読めるように、さらにはABCソングでアルファベットも読めるようになり、数字の1から20もしょっちゅう数えるようになりました。
まだ「ま行」から先は教えてないので覚えてないですが、実に楽しそうにノリノリでどんどん覚えていきます。(すべて覚えきったら追記します。)
お気に入りは言いやすい「か行」で、ある日の朝なんて起床して開口一番に「かきくけこぉぉぉ!!」とか言ってました。
もっと早い段階で「あいうえお」を言えるようになったお子さんも全然いると思いますが、うちの子は私の周りでは最速で覚えたのと、なにより息子がノリノリでひらがなを覚えていくので、うちのひらがな学習方法はなかなかおすすめです。
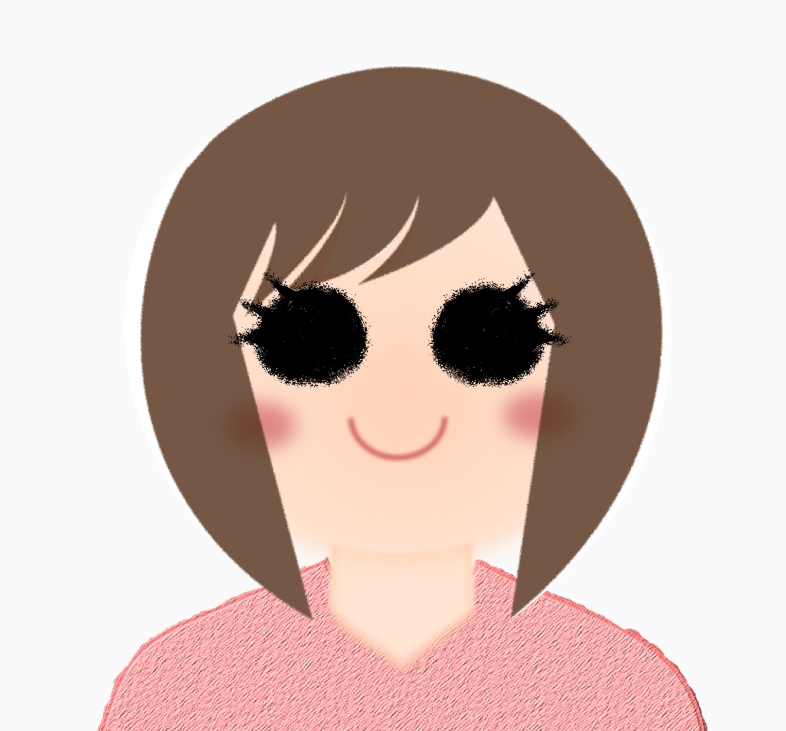
この記事ではうちの息子がひらがなを覚えている具体的な方法を紹介します。
早いうちにひらがなを教えようと思ったわけ
息子はオーストラリア在住の日豪ハーフなので、ママと常にべったりな幼児期は日本語優位でも、学校に通うようになったら必然的に英語優位になってしまいます。
なので就学前はできる限り日本語に触れさせよう!むしろ日本語メインで暮らそう!というのが我が家の方針です。
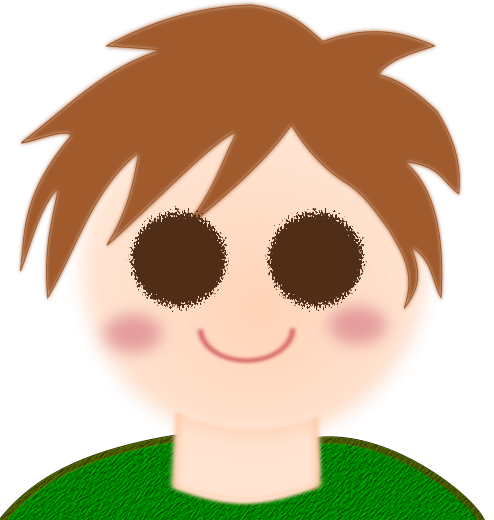
パパも日本語がまあまあ話せるのでその方針に大賛成。
アルファベットを覚えても単語は読むことができない英語と違い、日本語はひらがなを覚えてしまえば自分で絵本やマンガが読め、さらにそこから新しい言葉を学ぶこともでき、早い段階からどんどん日本語を吸収することができます。
幼いうちは全てのものが遊びであり新鮮で、学習意欲もとても高いです。
なので、ひらがなを覚える作業を「勉強=億劫」という風に感じない、遊びの延長として出来てしまう2歳前の時期からひらがなの習得をスタートさせようと思いました。
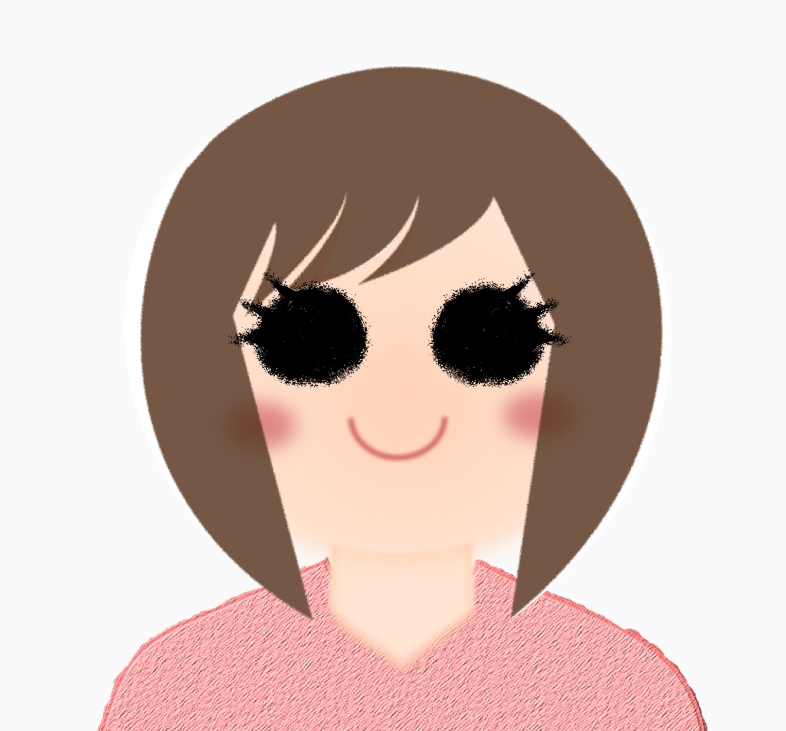
でも決して無理強いはせず、遊び感覚というのがポイントです!
息子の言語環境
息子が普段どのくらい、どのように日本語に触れているのか、母国語である英語との関わり合いはどの程度なのかをまとめてみました。
こんな感じの環境でやっています。参考までに。
ひらがなの勉強方法と使用した教材
ひらがなの勉強方法は一種類だけではなく、色んな方法を組み合わせて生活の中でひらがなに触れる機会をたくさん作ることを心がけました。
YouTube などで「あいうえお」の歌を聞かせる
まず一番初めに取り入れたのは、みんな大好きYouTube動画です。
歌のリズムにのせて楽しみながらひらがなの五十音にざっくりとでいいので馴染んでもらいます。
小さい子に動画を見せるのは賛否両論あるかと思いますが、うちではなるべく「親も一緒に参加(歌ったりわかりやすい解説をいれたり)しながら」見せるようにしています。
そうすることで「動画→子供」の一方通行的な受け身状態になるのを防ぎます。
あいうえおの歌動画を見る時は、ママも一緒に歌ったり踊ったりしながらだと子供にとってインパクトが全然違います。
あいうえおソングは色々ありますが、まずはお子さんの興味を引くような、好きなキャラクターなんかが出てきたりする楽しい動画を選んであげましょう。
だんだん慣れてきて、お子さんがなんとなーく「あいうえお」を認識してきたら、あ行の歌、か行の歌、さ行の歌と行ごとに集中して覚えられるような歌がおすすめです。
ちなみによく、「出だしの「あ」が難しくて最初からつまづく」という意見を耳にしますが、うちの子はEテレの「デザインあ」という、やたら「あ」の文字が出てくるシュールでインパクトのある短い番組をよく見ていたので、一番最初に「あ」は覚えてしまったようです。
実はABCはあまり熱心に教えていないのですが、LEGO DUPLOのABCソングを何度も見せていたら勝手に覚えていました。
ひらがなよりアルファベットの方が覚えやすいのかもしれません。
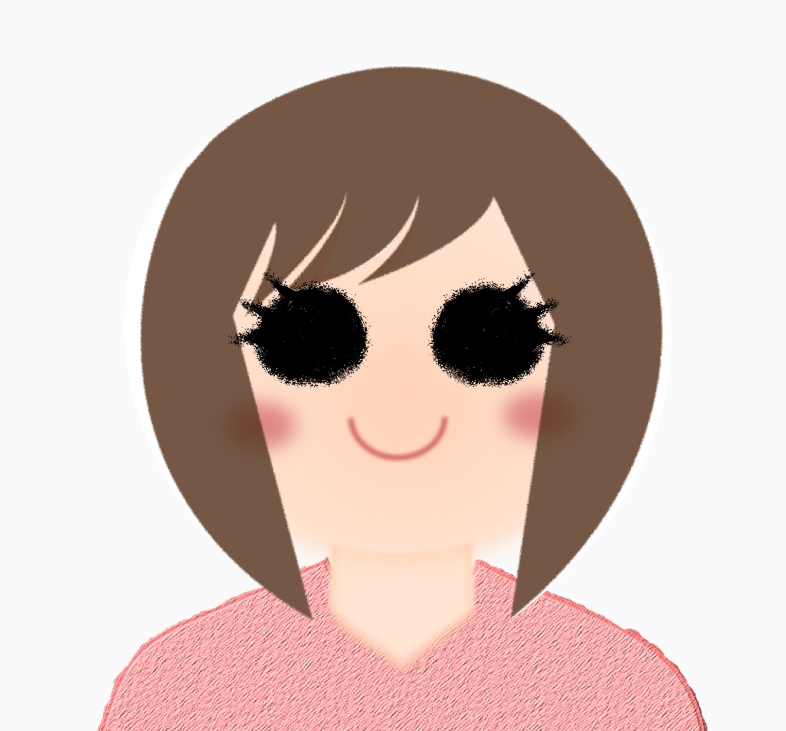
テレビもなかなか役立つと思う。
ちなみに我が家では Amazon Fire Stick TV で YouTube をテレビで見れるようにしてあります。
なので、大画面でひらがな動画が見れます。
動画をただぼーっと見ているだけだと一方的に情報が流れてくるだけで、小さい子供は情報を上手く理解できなかったりします。
最悪何も理解できずに無駄な時間を過ごしているだけということもあり得ます。
なので、親がいっしょに観て内容を分かりやすく噛み砕いて子供に伝えたり、一緒に歌ったり踊ったりするのが大切です。
スマホやタブレットの動画を子供に見せると画面が小さいので距離も近いし、ママやパパも他にやる事があるので毎回一緒に観るのは難しいです。
でもテレビの大画面なら、ママも家事の片手間にテレビを見て一緒に歌ったり補助したりして参加できます。
大画面だと画面から離れて見ることができるので繰り返し見ても目が疲れにくいですし。
スマホやタブレットは子供から取り上げるのが大変ですがテレビなら親がリモコンで操作できるので、制御しやすいというメリットもあります。
親が定期的に「あいうえお」を連呼する
親が日ごろから「あいうえお」を連呼していると子供は真似をしてすぐに覚えます。
うちの息子は私が「あー」というとすぐに「いー」と返してくれ、交互に言い合って最後に2人で「おー!!」と謎のハイテンションジャンプをキメるという遊びをします。
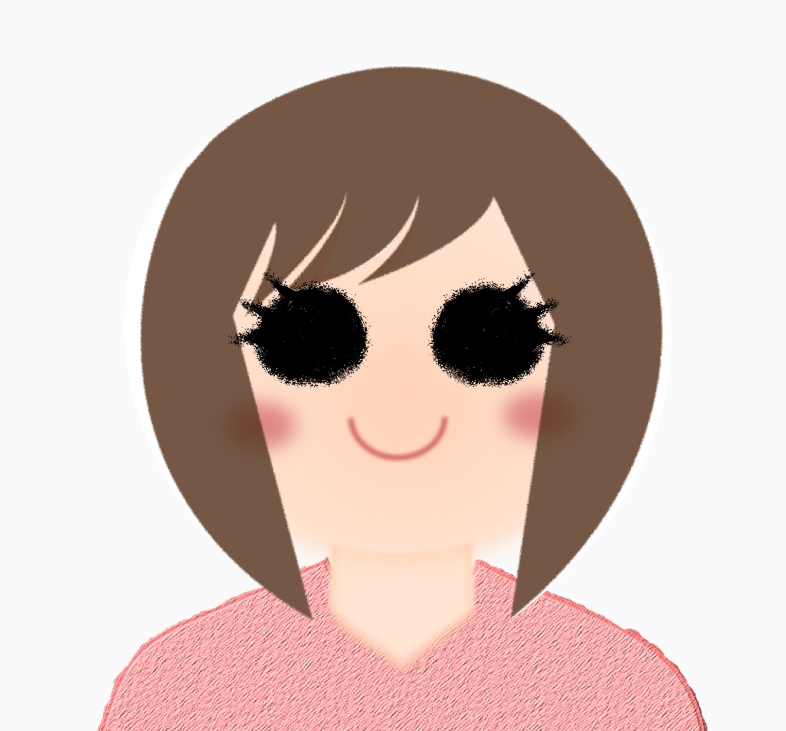
息子はこの遊びがやたらお気に入りで、1日何回も繰り返します。
「あいうえお」だけでなく、数字も私が事あるごとに「ママ手が離せないから10秒だけまってね、い~ち、に~」という風にしょっちゅう数えていたので、 1歳半前にはすでに自分で1から10までを何となく口ずさみ、2歳1ヶ月でスムーズに数えて読めるようになりました。
(数字の読みはYouTube動画&木製の数字パズルみたいなものを与えたら遊びながら読めるようになっていました)
ひらがな絵本を一緒に読む
ひらがなに関連した絵がかいてあるひらがな絵本をお子さんに読んであげるのもおすすめです。
「あ」なら「アリ」、「い」なら「犬」の絵や写真が文字のそばに描いてあるようなやつです。
はじめてのひらがな絵本はできるだけシンプルで身近なものが載っているものがよいと思います。
うちでは「はじめてのあいうえお」という本を使いました。小さくてイラストもシンプルかつ身近なものが多いのでおすすめです。
もっと年齢が上がってきたら、ひらがなのボタンを押すと発音や関連単語が再生されたり、単語のクイズを出してくれたりする電池入りの音が出るひらがな絵本もかなりおすすめです。
息子はボタン押すの大好きなので、どんどん押してひらがな音や単語の音声を真似して発音しています。
喋るあいうえお絵本で新たに言葉を覚えさせるというよりは、復習用に使っています。
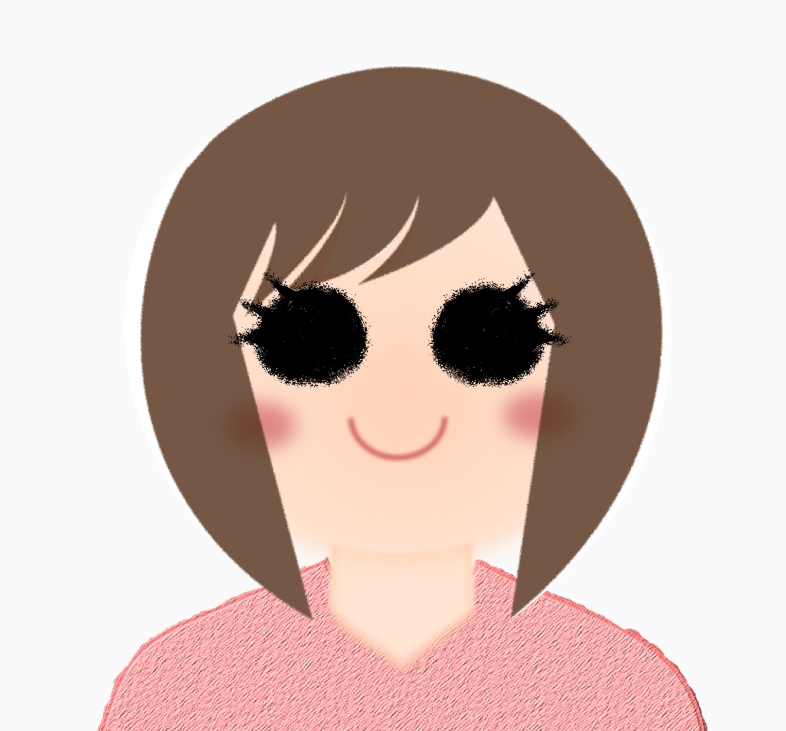
年齢が上がれば自分でもどんどん新しい言葉を覚えると思います。
ママと一緒にじっくり覚えたひらがなを1人で楽しく復習するのにとってもよいツールです。
ひらがなカードでクイズ
絵本も良いのですが、うちではひらがなカードの方が大活躍でした。
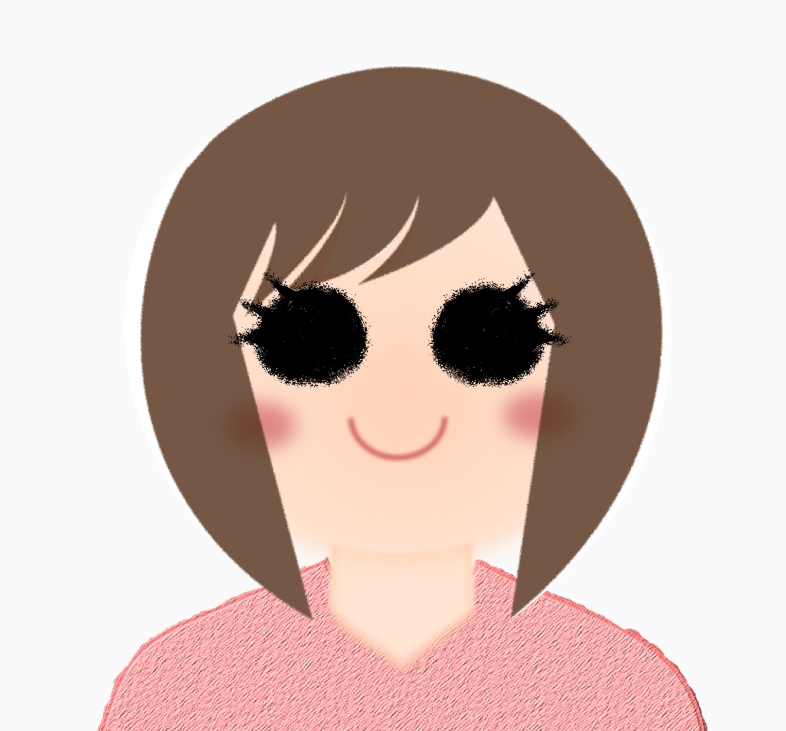
ひらがなカードとは、表が「い」なら裏に犬の絵が書いてあるような、ひらがなの裏に関連した絵が描いてあるやつです。
絵本だと息子は自分でどんどん高速でめくっていってしまったり、いつも最初の方だけ眺めて飽きたりするんですが、カードなら覚える行のカードだけに集中して勉強できます。
かるたみたいなゲームもできるし、カードの文字だけをみせて「これなーに?」とクイズを出すようにして遊べます。使い方色々です。
うちでは「くもん」のひらがなカードを使っています。シンプルでカードの作りも丈夫でおすすめです。
くもんのひらがなカードは身近なもののイラストが多いですが、息子がまだ知らないもののイラストも少しあるので、そういうものは自分でネットで無料素材を探してきて、カードのイラストを差し替えています。
オリジナルの「け」の裏の絵が「けむし」になってて正直微妙なので、息子の大好きな「けーき」の絵に差し替えちゃいました。
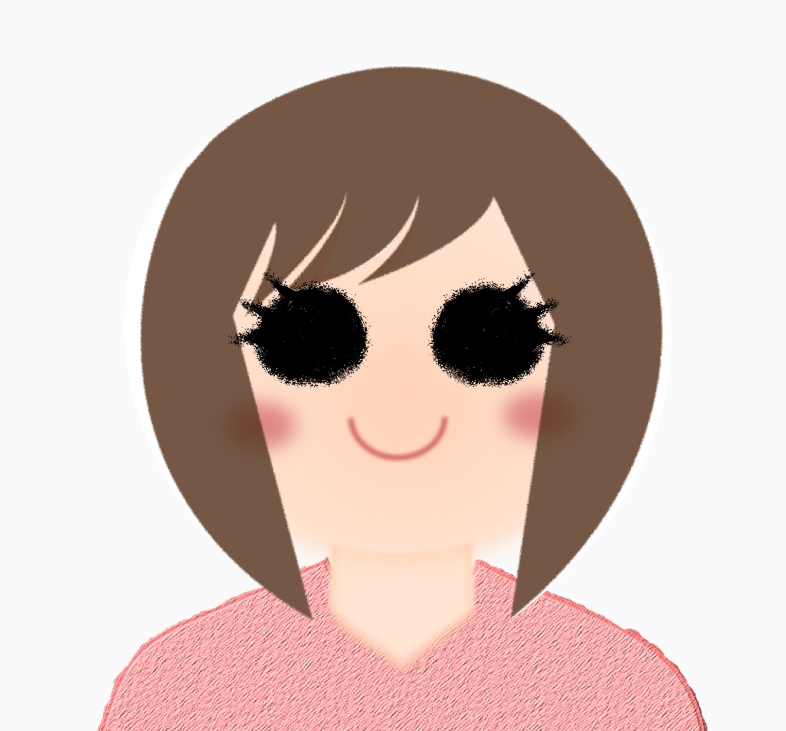
好きなものだとすぐ覚えます。
なかなか覚えられない文字は、大きいカードを自作してインパクトを大きくするなどしていました。
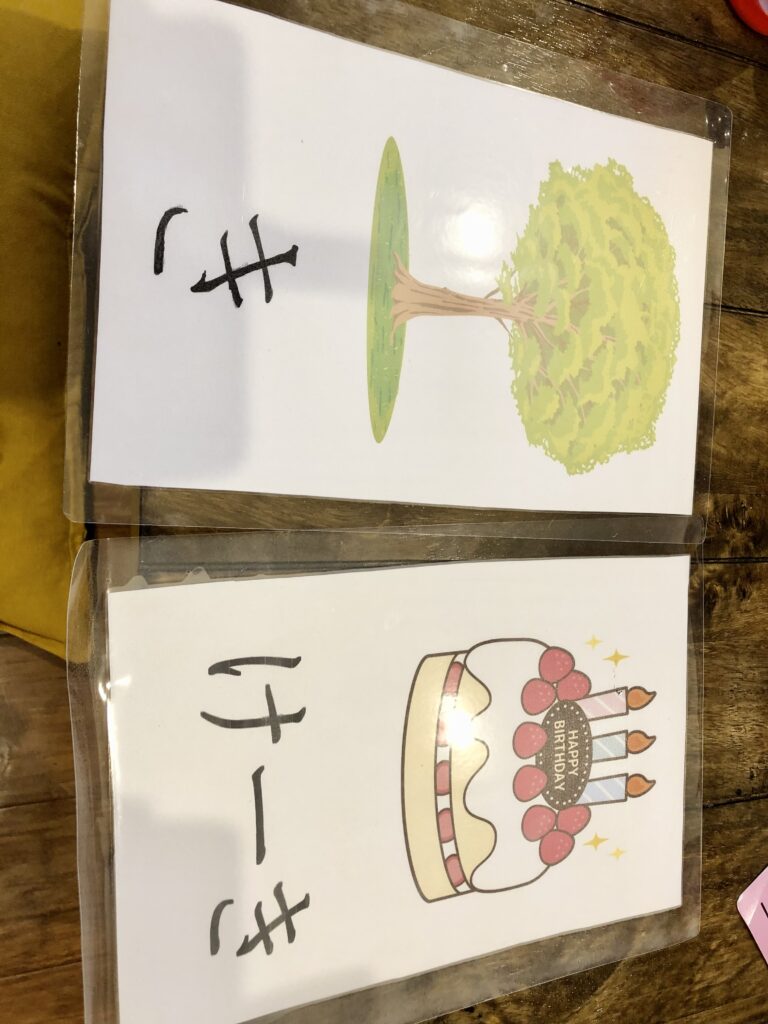
ラミネーターを使えばペラペラの印刷物の強度を格段にあげることができます。
ひらがな一覧表を一番目に付くところに貼る
ひらがな表は定番のお風呂場ではなく、息子がいつも遊んでいるリビングの一角とコーヒーテーブルに貼って常に目に付くようにしています。
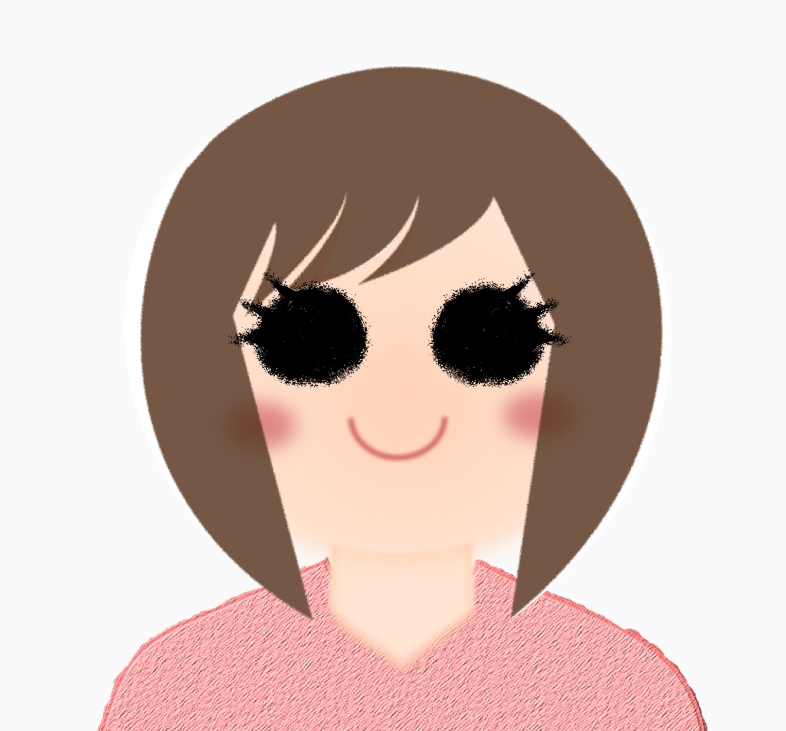
遊びの合間にたまにひらがなを読んだりしてくれます。
小さい子だとひらがな表を破いたりぐしゃぐしゃにしたりすることもあるので、ひらがな表は上で紹介したラミネーターで補強するか、破れない素材の物を選ぶといいと思います。
正しく言えたり読めたりしたら褒めたり一緒に喜ぶ
お子さんがひらがなを口ずさんだり文字を読んだりしたら、褒めたり喜んだり、「そうだね〜!」などでも良いのでポジティブな反応をしてあげましょう。
我が家ではモンテッソーリやシュタイナー教育を意識しているので、「すごいねー!」と褒めるより「できたー!」「やったー!」とテンション高めに声かけしています。
そうする事で「褒めてくれるから覚える」ではなく「覚えて正しく言える・読める事への達成感」を感じてもらえたらいいなーと思っています。
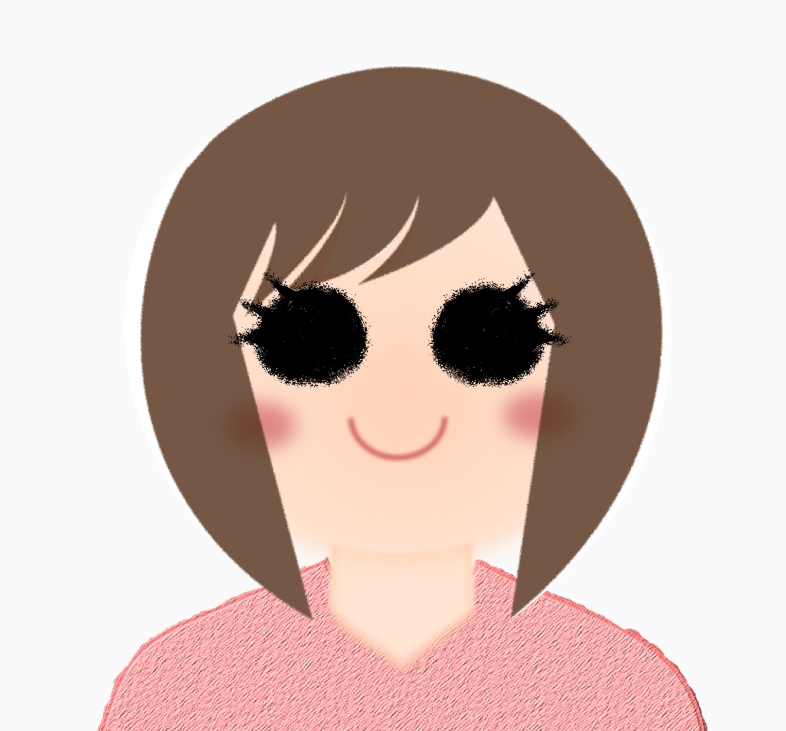
まだ小さいので本人からしたらどっちでも同じなのかも知れませんが。。。
ひらがなを教える時のポイントと注意
「りんご」「いぬ」などの実際に目で見たり触れたりできる名詞や、日常的によく使う「食べる」などの動詞などとは違って、ひらがなはただの音でありそれ自体には意味がありません。
そんなひらがな五十音順を教える時には気をつけたいポイントがあります。
決して無理させず、楽しい雰囲気で
これはとても重要な事です。子供が覚えるのを嫌がっているのに無理に教えようとすればひらがなを嫌いになってしまいます。
子供が楽しんで、遊び感覚でひらがなを覚えられるような工夫が大事です。
子供の反応を見て、興味を持ってくれなかったら方法を変えてみましょう。
一度に詰め込みすぎない
早く覚えて欲しいからと一度にたくさんのひらがなを詰め込むのも逆効果です。情報が多すぎると飽きてしまいます。
今週は「あ行」、来週は「か行」という風に行ごとに少しづつ進んでいって、3歩進んだら2歩下がって復習するくらいの速度で十分です。
特に読めるようになるのは時間がかるので、あまりどんどん先に進めないように気をつけましょう。
教材は一つではなく数種類組み合わせる
ひらがなを学ぶときはいろんな教材や方法を組み合わせて取り入れると記憶にも定着しやすいです。
例えば、うちではまずYouTubeの動画で新しいひらがなを紹介し、動画を毎日繰り返し見たりひらがなカードを使って一緒に遊びながら定着させ、自分一人で見る用にあいうえおの絵本とひらがな一覧表を使用しています。
知っている物、好きなものと関連付けておぼえさせる
ひらがなにあまり興味を示さなくても、好きなものを取り入れれば自ずと興味がわいてくるし、覚えるのも早いです。
お子さんが車が好きなら「ほら、クレーン車の「く」だよー」なんていう風に結びつけてしまえばいいのです。
その際はやはり自作カードなど視覚に訴えられるものがあったほうが良いですね。
ママやパパと歌うように、クイズ感覚で、楽しく!
ひらがな五十音順は子供にとってはなんだかよく分からない意味の無い謎の音なので、歌のように楽しく覚えたり、読み方もクイズのように楽しみながら学ぶのが1番です。
楽しければ子供もモチベーションが上がってどんどん覚えてくれます。
繰り返し反復、特に忘れかけていそうな頃に復習する
大人でもそうですが、短期記憶を長期記憶として定着させるには、反復学習、特にちょっと忘れかけてた頃にもう一度思い出してもらうというのがとても有効なのだそう。

脳科学に基づいてるらしいよ!
ガチガチに復習しなくても、あいうえおの歌の動画をサラッと1回見るだけでも十分な復習になると思います。
文字を読めるようになるタイミングは人それぞれ!
息子はたまたま早い段階から文字を覚えるのに興味を示し、文字を文字として認識するのも早かったですが、子供の成長は千差万別です。
息子もひらがなは読めても2語文が出るのは周りよりだいぶ遅かったです。
例えお子さんがなかなか文字を覚えなくても、今はまだその子にとってその時期では無いというだけです。
お子さんの様子をよく観察して文字を学ぶのによい時期かどうかを見極め、まだ早そうなら適切な時期が来るまで気長に待ちましょう。

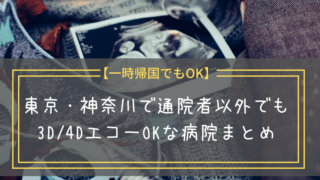

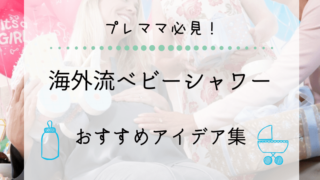
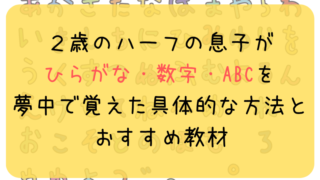



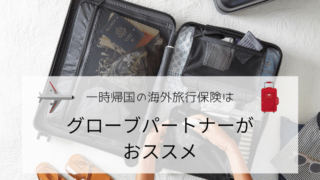
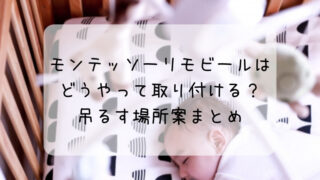


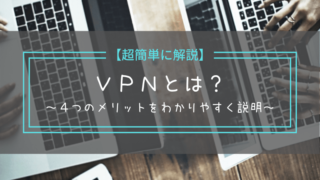


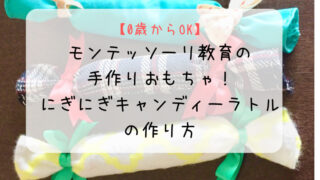



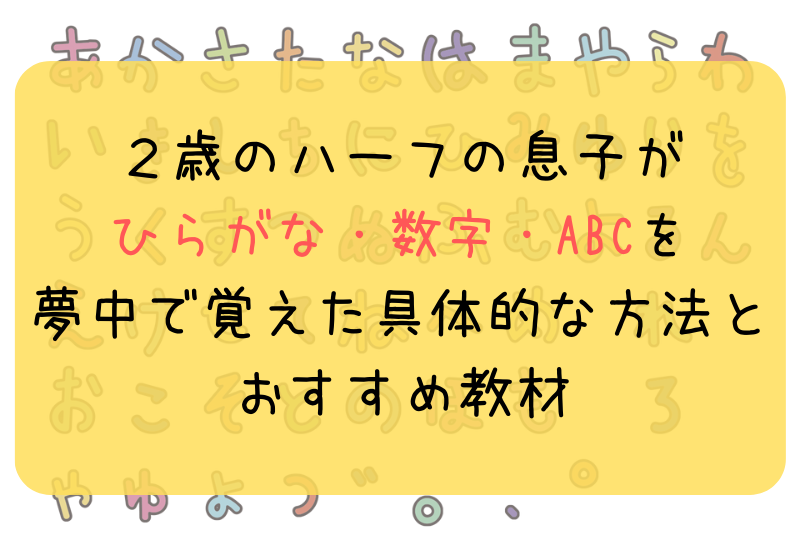







コメント